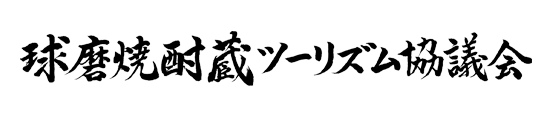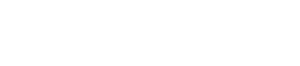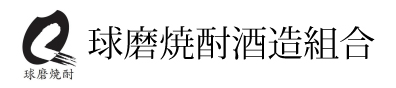球磨焼酎
500年の時を経て育まれるブランド
熊本の最南端に位置する人吉球磨は、九州山系の懐深い山々に囲まれた盆地にあります。その美しい山々から良質の水が流れだし日本三急流のひとつである清流球磨川を作り出しました。盆地特有の寒暖の差が激しい気候と風土が育む費かな大地が、熊本でも有数の米どころを作り上げ、米から造る極上の本格焼酎「球磨焼酎」が誕生しました。
人吉球磨地域に蔵をかまえる27の蔵元は、複数の個性ある銘柄を持ち、すべてをあわせると200以上のプランドを誇っています。杜氏たちの手で丹精込めて作られた球磨焼酎は、芳醇な香りと深いコクが楽しめるのが特徵で、多彩な味のバリエ-ションを作り上げています。
「球磨焼酎」は、日本に5つしかない産地呼称が認められた本格焼酎のプランドのひとつになり、地理的表示规定(球磨焼酎の世界的友保護)と地域団体商標登録(地域プランドの保護)を受けています。
製造方法
(1)お米を蒸す
球磨焼酎の原料はお米です。 お米を洗って水を吸わせ、蒸します。
(2)製麹(麹つくり)
【蒸した米に、麹菌を生やしていく工程】
米を洗って水を吸わせ、蒸し、冷ましてから麹菌を混ぜ、35℃前後で、約40時間かけて麹菌を生やしていきます。この麹菌が生えたものを『麹』といいます。この作業を麹室(こうじむろ)という保温された部屋で、手作業で行う場合を、手づくりといいます。
(3)一次仕込み(一次もろみ)
【酵母(菌)を増やしていく工程 酒母や酛(もと)ともいいます】
アルコールをつくる酵母を、いらない菌を防ぎながら、大量に増やして、たくさんアルコールをつくる準備をします。かめなどの容器に水を入れ、培養した酵母を加えて、麹を加えます。これを一次仕込みと呼び、仕込んだものを一次もろみといいます。麹から与える栄養を食べて、アルコール発酵しながら、酵母が増えていきます。
(4)二次仕込み(二次もろみ)
【アルコールを本格的につくる工程 主発酵】
大量に酵母を増やした一次もろみに、水を加えてアルコールなどの成分を薄めて、更にアルコールをつくれる環境をつくり、蒸した米を食べ物として加えて、本格的にアルコールをつくります。これを二次仕込みと呼び、仕込んだものを二次もろみといいます。
(5)蒸留
【焼酎原酒をつくる工程】
アルコールが大量にできた熟成した二次もろみを、蒸留機に入れて加熱し、蒸発してきた成分を冷やすと液体になります。これが焼酎の原酒となります。
発酵を終えた二次もろみは、蒸留釜で加熱され、アルコール蒸気となり、これが冷やされ液化し、焼酎として取り出されます。
(6)貯蔵
蒸留した焼酎は、貯蔵容器に移し、密封貯蔵します。この貯蔵で焼酎の味香りが次第に長熟し、深いコクのある球磨焼酎になります。球磨焼酎にはタンク・カメ・樽・瓶の4つの貯蔵方法があります。
【日本語】球磨焼酎PV